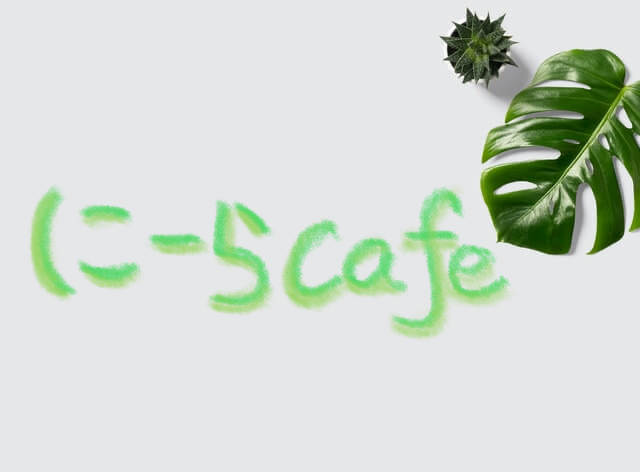最近ではコンビニ、自販機、カフェどこでも気軽にお茶を手にすることができます
お茶のほろ苦さや香りが魅力ですよね
日常で当たり前のお茶ですが、日本茶は一種類ではありません
お茶屋さんでどんなお茶を選ぼうか悩んでいると
お茶の分類が多くて違いがわからないことありませんか?
深蒸しってなに?
玉露高いなって思いませんか?
私も違いがわからず、こっそりネットで調べたり、店員さんに聞いたりして頼んでいました
そんなときに参考になれば嬉しいなと思い、
日本茶のことについて簡単にまとめてみたのでみていきましょう!
目次
そもそも日本茶ってどんなもの?

日本茶の簡単なプロフィールです
- ツバキ科ツバキ属の永年生活常用樹
- 学名:カメリア・シネセンス
- 中国種(日本茶)とアッサム種(紅茶)の二種類ある
- 花は白色で8から12月に開花する
- 摘みっとた生葉から日本茶ができる
- 30年から50年と栽培寿命は長い(江戸時代から生きながらえている樹もある)
日本茶の分類
日本茶にはいくつか分類されます
よく聞く煎茶や玉露などの違いに触れていきます
煎茶(せんちゃ)
- 日本茶と言えばの代名詞
- お茶は爽やかな香り・旨味・渋みが調和して綺麗な緑色
- 製造工程は、蒸し→粗揉→揉捻→中揉→精揉→乾燥であり機械や手揉みで行う
- 揉まれ続け、茶葉は針みたいに細い
- 苦みを感じやすいので和菓子との相性がよい
深蒸し緑茶(ふかむしりょくちゃ)
- 煎茶よりも蒸す時間が2から3倍長い
- 渋みが抑えられて、甘みが増す
- 葉が細かくなりやすいため粉が多いため、お茶は濃い緑色
- 苦いお茶苦手の人におすすめ、お茶の甘みを堪能できます
玉露(ぎょくろ)
- 有名な最上級のお茶
- 実は、製造工程は煎茶と同じ
- 茶樹に当たる日光を避ける栽培方法
- 特殊な栽培方法と手摘みと手間がかかる
- お茶は煎茶と異なり色はほのかに黄色
- 味は旨味を感じ、ずっしりとした飲みごたえがある
- 日光を避ける期間が短いものを『かぶせ茶』という。煎茶と玉露のハーフ。
抹茶(まっちゃ)
- 乾燥したお茶を石臼で挽いて作る微粉末状のお茶
- 抹茶の原料は、『碾茶(てんちゃ)』という
- 玉露と同じように日光を避ける栽培方法
- 他のお茶にない唯一揉まないで作られる
- 製造方法は蒸熱→冷却散茶→荒乾燥・本乾燥→選別→煉り乾燥
- 一定時間熟成させてから石臼で少量ずつ時間をかけて挽く
- お茶は濃い緑色で芳醇な香り、苦みの奥に旨味を感じる
- 和菓子と相性は良い
番茶(ばんちゃ)
- 絶対飲んだことのある普段使いのお茶
- 晩茶とも表記され、晩い時期に摘む
- 新芽が伸びすぎの硬い葉、一番・二番茶の後の硬い葉、夏の三番・四番茶、整枝で刈り取った葉・茎、煎茶の工程で選別された大形の葉達で作られる
- お茶は、緑がかった半透明でペットボトルのお茶の原料として使われる
- ゴクゴクと飲める、さっぱりしているのでいつでも飲みやすい
玉緑茶(たまりょくちゃ)
- 製造工程の殺青(酵素の動きを止めること)が蒸しと釜炒りがある
- 揉み工程が煎茶に比べ少ない
- 花のような独特な香り
- 茶葉の形は勾玉のような形
焙じ茶(ほうじちゃ)
- 最近人気のお茶
- 番茶などを褐色になるまで強火で焙煎したもの
- お茶は褐色で香ばしい香り
- さっぱりな飲みごごち、食後におすすめ
- 一番茶の遅い時期の葉が上質であり、上質な茎茶を焙じた『茎焙じ茶』もある
- 親戚に白米を焙煎したものと煎茶・番茶など50%混ぜた『玄米茶』がいる
参考文献:「日本茶の全てがわかる本,農山漁村文化協会,2021年3月」
まとめ:色んな日本茶を飲んでみよう!

素の日本茶葉は同じでも、作り方やお茶の葉の摘む時期で分類されます
まとめると…
- お茶の苦み、渋みが好みの方は、煎茶
- お茶の苦み、渋みが苦手の方は、甘みを感じる深蒸し緑茶
- 日本茶の旨味を知りたい方は、抹茶や玉露
- 晴れやかな香りを楽しみたい方は、玉緑茶
- さっぱりとしたい方は、番茶や焙じ茶
このように味覚の好みがわかると選びやすいのかなと思います
実際には、お茶の品種や栽培地、作り手さんによっても味や風味が違うので奥深い世界です
色んな種類を飲んでみて、あなたのお気に入りの日本茶を探してみましょう!